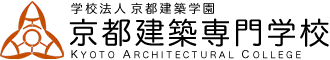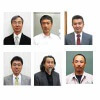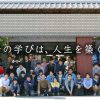| 設計製図1 A/B | 1年次 | 担当教員:杉江 崇・桐浴 邦夫 |
| 授業の目的 | 製図と設計の基礎を学ぶ | |
| 授業の概要 | 製図の基礎と、木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造の模写を通じてそれぞれの建築設計の基礎を学ぶ。また自由設計として小住宅や鉄筋コンクリート造建築の設計を行う | |
| 設計製図2 | 2年次 | 担当教員:髙橋 勝・円満字 洋介 |
| 授業の目的 | 鉄筋コンクリート造の理解を通して、より規模の大きなかつ複雑な建造物に対処できる力の修得 | |
| 授業の概要 | 鉄筋コンクリート造の実際を、前半の模写、後半の自由設計により学びながら、建築設計に関する一通りの知識・技術の習得を目指す | |
| CAD情報A/B | 1年次 | 担当教員:山口 英樹 |
| 授業の目的 | コンピュータの基礎知識を学び、建築CADによる製図法を習得する | |
| 授業の概要 | 前期は、jw_cadのコマンド、基本的な使用方法を学ぶ。後期は自由設計の住宅をCADで表現する。また、3D-CADの基本操作を学ぶ | |
| 建築計画 | 2年次 | 担当教員:髙橋 勝 |
| 授業の目的 | 建築設計に直結する計画学の基本を学ぶ | |
| 授業の概要 | 人間の生活・行動・意識と空間との対応関係から建築計画にアプローチする | |
| 計画演習 | 2年次 | 担当教員:髙橋 勝 |
| 授業の目的 | 建築計画を実践的に建築設計を通して学ぶ | |
| 授業の概要 | 建築計画を実例研究と課題演習を通じて習得する | |
| 日本建築史 | 1年次 | 担当教員:桐浴 邦夫 |
| 授業の目的 | 日本における社寺を中心とした建築の歴史を概観し、古建築を見る目を養う。 | |
| 授業の概要 | 古代、中世、近世と、社寺を中心に、代表的な建築を紹介しながら、時代背景などとともに日本建築の歴史をたどる。とりわけ時代別の意匠や構造の特徴を学ぶことを重視し、それぞれの建築の見どころを理解する。 | |
| 住居史 | 1年次 | 担当教員:桐浴 邦夫 |
| 授業の目的 | 日本住居の歴史の概要を理解し、今の我々の住居がどのような経緯で形作られたかを理解する。 | |
| 授業の概要 | 日本住宅の二大様式である寝殿造と書院造を中心に、宮殿建築、町屋、民家、茶室・数寄屋造について学ぶ | |
| 環境工学A/B | 1年次 | 担当教員:中 美加子 |
| 授業の目的 | 私たちを取り巻く自然現象についての理解を深め、建築の設計に必要な知識を身につける | |
| 授業の概要 | 前期では光と音の基本的な考え方を学び、後期では快適な温度の基準、断熱や結露の仕組みについて学ぶ | |
| 建築設備A/B | 2年次 | 担当教員:中 美加子 |
| 授業の目的 | 給排水や空調、電機など快適に建物を使用するための設備について、基本的な用語を知り、その仕組みについて考える | |
| 授業の概要 | 建築設備Aでは水や電気を使用するための設備を、建築設備Bでは空調や防災のための設備をそれぞれ考える上で必要な用語や仕組みを学ぶ | |
| 構造力学1 A/B | 1年次 | 担当教員:浅野 清昭 |
| 授業の目的 | 様々な構造体の支点に生じる反力・応力、外力によって構造体内に生じる応力・応力度をそれぞれ理解し、その算出方法を学ぶ | |
| 授業の概要 | 前期では力とは何かを身近な現象を通して理解し、力の釣り合いによって構造物が成立していることを学ぶ。後期では構造物の中に生じる応力・応力度について理解する、また許容応力度設計の概要について学ぶ | |
| 構造力学2 A/B | 2年次 | 担当教員:浅野 清昭 |
| 授業の目的 | 鉄骨構造とその問題点、不静定構造について学ぶ | |
| 授業の概要 | 前期では鉄骨構造をイメージしてトラスの解法、柱の座屈、梁のたわみについて学ぶ。後期では不静定構造について学び、総復習として静定構造の一連の解法を問題演習として振り返る | |
| 建築一般構造 | 1年次 | 担当教員:山口 英樹 |
| 授業の目的 | 木構造・鉄筋コンクリート構造・鉄骨造において、建築材料がどのような仕組みで建築物になるのかという基礎知識を学ぶ | |
| 授業の概要 | 主として木造軸組み構造についてその構造、仕上げ方法を学習し、その他の枠組み壁構造、鉄筋コンクリート、鉄骨造については、基本的な構造の特徴を学ぶ | |
| 木構造 | 1年次 | 担当教員:山口 英樹 |
| 授業の目的 | 木造軸組工法の概要を知ると共に、軸組み工法の設計法を学ぶ | |
| 授業の概要 | 木造2階建て(軸組工法)の確認申請に必要な程度の構造知識と性能表示制度の構造検討ができるようになる | |
| 鉄筋コンクリート構造 | 2年次 | 担当教員:浅野 清昭 |
| 授業の目的 | 鉄筋コンクリート構造の工法、構造計画、構造計算の基礎知識を得る | |
| 授業の概要 | 日本における構造設計の流れを開設。鉛直荷重、地震力、風荷重の求め方を解説したのち、鉄筋コンクリート構造の大梁、柱、スラブ、基礎の構造設計法を学ぶ | |
| 鉄骨構造 | 2年次 | 担当教員:浅野 清昭 |
| 授業の目的 | 鉄骨構造の工法、構造計画、構造計算の基礎知識の習得と、2次設計の基礎知識を習得する | |
| 授業の概要 | 鉄骨構造の概説ののち、鉄骨構造の大梁、柱の構造設計接合部の構造設計法を学ぶ。加えて、2次設計(層間変形角、剛性率、偏心率、塔状比、保有水平耐力)について解説する | |
| 木質材料 | 1年次 | 担当教員:杉江 崇 |
| 授業の目的 | 建築材料の物理的、科学的物質、製法、その他特性を知り、適材適所の使用を理解する | |
| 授業の概要 | 木質構造を中心に、焼成材(瓦など)、ガラス、石材、左官材料といった木造建築物に関連の深い材料を取り扱う。実物サンプルや実験データ、実例写真等を通して体系的に学習する | |
| 建築材料 | 1年次 | 担当教員:杉江 崇 |
| 授業の目的 | 建築材料の物理的、化学的性質、製法、その他特性を知り、適材適所の使用を理解する | |
| 授業の概要 | コンクリート、鋼材を中心にその他材料を取り扱う。実物サンプルや実験データ、実例写真等を通して体系的に学習する | |
| 建築施工法A/B | 2年次 | 担当教員:浜野 豪 |
| 授業の目的 | 建築の生産の基本、順序、工事別の施工技術を理解し、建築の品質向上に努める | |
| 授業の概要 | 工事順序に従った授業を行い、各工事の施工ポイントを理解する。また、施工図を描くことで建物を造ることへの理解と関心を深める | |
| 建築積算A/B | 2年次 | 担当教員:浜野 豪 |
| 授業の目的 | 各種工事の数量算出方法を知り、工事費の構成を理解する | |
| 授業の概要 | 各種工事の概要を説明し、演習を行って数量算出の理解を深める | |
| 建築法規A/B | 2年次 | 担当教員:永良 勲 |
| 授業の目的 | 実務に使える建築法規について基本的事項を理解、二級建築士学科試験にも使える知識を習得する | |
| 授業の概要 | 建築基準法について「なぜ?」を意識しながら、法令集の読み方について学ぶ | |
| CAD演習A/B | 2年次 | 担当教員:山口 英樹 |
| 授業の目的 | CADによる2次元製図、3次元CGおよびプレゼンテーションの実践力を身につけ、卒業設計に活用する | |
| 授業の概要 | 前期は3次元CGソフト(SketchUp)の基礎的な操作方法を学習する。後期は実践的なプレゼンテーションテクニックを身につけ、卒業制作に活用する | |
| 意匠演習 | 1年次 | 担当教員:山本 豊 |
| 授業の目的 | 透視図の作成を行うことにより、立体的な表現と形の見え方を理解する | |
| 授業の概要 | 作成にあたり、授業開始時に手順や図法の説明を行う。平面図と展開図のつながりを理解し、透視図を描く。手で書く実習をすることで、現場で対応できる表現技術を習得する | |
| 建築測量A/B | 1年次 | 担当教員:城市 智幸 |
| 授業の目的 | 測量学の基礎を学ぶ | |
| 授業の概要 | 授業の概要:各種の測量における注意点・方法・使用目的などを理解する | |
| インテリアデザイン | 1年次 | 担当教員:山本 豊 |
| 授業の目的 | 西欧、近代日本におけるデザインの流れを概観し、インテリア計画の手法を理解する | |
| 授業の概要 | 西欧や日本のインテリアの思想とデザインについて講義する。住まいの中にある建築の演出要素について考える | |
| 西洋建築史 | 1・2年次 | 担当教員:桐浴 邦夫 |
| 授業の目的 | 西洋建築の諸相を歴史的に概観することによって、西洋建築の総括的な理解を目指す | |
| 授業の概要 | 古代エジプト建築を取り上げた後、西洋の建築を古代ギリシアからバロックまで歴史的に順を追って解説する | |
| 近代建築史 | 2年次 | 担当教員:桐浴 邦夫 |
| 授業の目的 | 近代建築を概観し、現在の我々をとりまく建築がどのような経緯でつくられてきたのかを理解する | |
| 授業の概要 | 西洋と日本の近代における建築の展開を概観する。西洋に起こった産業革命、19世紀末の造形運動、モダニズムとそれぞれの日本への影響を見る。さらには日本独自の展開と近世以前からの連続性にも一瞥する | |
| 卒業設計 | 2年次 | 担当教員:髙橋 勝・円満字 洋介 |
| 授業の目的 | ここまでに学んだ建築知識・技術を集大成し、卒業設計と言う形で表現する。 | |
| 授業の概要 | 建築に関する全知識の集大成として、卒業設計を完成し、各自プレゼンテーションを行う。技術的側面ばかりではなく、表現面においても社会に対してなんらかの提案となることが求められている | |
工業専門課程2年制 夜間
最短で、建築士(一級、二級、木造)受験資格。
社会人や大学生、さまざまな人が在籍、基礎から建築を学ぶ。
働き...
設計製図1 A/B
1年次
担当教員:杉江 崇・桐浴 邦夫
授業の目的
製図と設計の基礎を学ぶ
授業の...
1・2時限目(18:20~21:30)は「必修科目」。
0時限目、1年のインテリアデザイン、建築測量、2年の日本建築史ABはオ...
氏名
桐浴 邦夫(きりさこ くにお)
役職
副校長
担当科目
設計製図、日本建築史、住居史、西洋建...
建築科二部2年生 藤原 秀織さん
〝 建築士の資格を早く取って独立したい! 〟
小さいころから日本の建築に興味を持っていたことと...
■町家改修作品(1年生)
■卒業設計作品(2年生)
...
建築科二部(夜間)では、聴講生を受け入れています。
高等学校を卒業、あるいはそれと同等以上の人ならば、どなたでも自由に学ぶことができま...