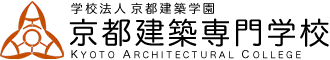「茶室の過去・現在・未来 シンポジウム」
建築家も文化人も、熱く語りたい!
日時:令和7年7月13日(日)13時~16時30分
場所:京都府立京都学・歴彩館(京都市左京区下鴨半木町1-29)
定員:350名
入場:無料(事前申込必要)
申込: https://tea-expo-kyoto.peatix.com/
<登壇者>
阿部仁史、伊住禮次朗、魚谷繁礼、桐浴邦夫、濱崎加奈子、藤森照信
詳しくは ↓
PDFファイル
============================
―町家で学ぶ伝統建築―
伝統建築研究科は、日本の伝統的構法を伝えてきた工匠たちが造った学校として、本校の特色である伝統建築について、より深く学ぶ学科です。
期間 : 2025 年4 月~ 2025 年12 月(前期:4 月~ 7 月、後期:10 月~ 12 月)
日程 : 下記の表を参照
時間 : 19:00 ~ 21:00
場所 : 京都建築専門学校よしやまち町家校舎(京都市上京区葭屋町通下立売下ル丸屋町260)および遠隔(Zoom)併用
受講資格 : 特になし(建築関係以外の方も歓迎です)
受講料 : 50,000 円(前期のみ、後期のみの方は、それぞれ30,000 円)
募集開始:3月3日 9:30~
募集人数 : 約30 名(町家校舎およびZoom10 名・Zoom のみ約20 名、先着順)
後期のみの受講の方も3/3からの募集期間中にお申し込みいただけます。
また後期に空きがある場合、8月9月頃に再募集いたします。
申込:追ってお知らせします(上記リーフレットをご覧ください)
| ■前期 和風建築の基礎 桐浴 邦夫・稲田朋代* |
||
| 1 | 4/16 | 和風建築史 和と日本の歴史 |
| 2 | 4/23 | 神社建築の形 |
| 3 | 5/7 | 伝来した寺院建築 |
| 4 | 5/14 | 国風化の時代 |
| 5 | 5/28 | 古代の宮都とすまい |
| 6 | 6/4 | 中世の和様と新しい建築 |
| 7 | 6/18 | 和室の成立 |
| 8 | 6/25 | 民家と町家 |
| 9 | 7/2 | 茶室と数寄屋 |
| 10 | 7/9 | 近世の建築 |
| 11 | 7/16 | 文化財建造物の保存 概要と事例* |
| 12 | 7/23 | 近代建築と和風 |
| ■後期 茶室と町家の基礎 桐浴 邦夫・丸山俊明* |
||
| 1 | 10/1 | 日本の住宅概要 |
| 2 | 10/8 | 茶室の見方 |
| 3 | 10/15 | 茶の湯と茶室建築 |
| 4 | 10/22 | 市中の山居 |
| 5 | 10/29 | わび数寄の空間 |
| 6 | 11/5 | 綺麗さびの空間 |
| 7 | 11/12 | 数寄屋の拡がりと煎茶の空間 |
| 8 | 11/19 | 近代の茶室と数寄屋 |
| 9 | 11/26 | 近代の建築家と茶室・数寄屋 |
| 10 | 12/3 | 京の町家 基礎編* |
| 11 | 12/10 | 京の町家 中級編* |
| 12 | 12/17 | 京の町家 上級編* |
| 稲田 朋代(いなだ ともよ):京都府教育庁指導部文化財保護課。1997 年京都府へ建築技師として入庁。2004 年教育庁文化財保護課へ異動後、文化財行政に従事。2009 年から重要文化財建造物保存修理現場において、調査・記録・工事監理に携わる。これまで、萬福寺松隠堂庫裏ほか2棟、知恩院本堂及び附廊下、聴竹居茶室ほか2棟等の現場を担当。
丸山 俊明(まるやま としあき):住環境文化研究所主宰。京都工芸繊維大学博士課程修了。学術博士。元びわこ学院大学短期大学部教授。元京都美術工芸大学教授。著書に『京の町家史』(住環境文化研究所2023)、『京都の歴史と消防』(大龍堂2022)、『京都の木戸門と番人』(大龍堂2022)、『京のまちなみ史』(昭和堂2018)など。 桐浴 邦夫(きりさこ くにお):京都建築専門学校副校長。京都工芸繊維大学大学院修士課程修了。東京大学博士(工学)。著書に『a+u/茶室33 選』(編著2022)、『茶室設計』(エクスナレッジ2020)、『茶の湯空間の近代』(思文閣出版2018)、『茶室露地大事典』(共、淡交社2018)、『近代の茶室と数寄屋』(淡交社2004)など。 |
||
_______________________________________________________________
- 伝統建築に興味を持っている人はもちろんのこと、一般に建築に携わっている人にも是非学んでいただきたいと思います。
- 特に建築にかかわっていない人も学ぶことができます。
- なるべくやさしく、伝統建築の基礎から少し応用的なところまで理解できるような内容となっています。
- 伝統建築研究科に学びながら、建築の基礎の知識を得たい、という人のために、建築科二部聴講生の制度があります。
============================
【受講申込書】
3月3日以降に公開します。
============================
参照:令和6年度(2024年度)伝統建築研究科(アドバンスドコース)
アドバンスドコースは令和8年度以降に行う予定です。(上記、令和6年度のものは参考としてご覧ください)
============================
おかげさまで、無事終了しました。
―オンライン市民講座―
オンライン市民講座 第1回 『江戸の町家・京の町家』
大河ドラマ「べらぼう」で蔦重が駆け巡る江戸の町なみ。その江戸の町家と町なみのなりたちを、京都の町なみや町家と比べながら概観し、特徴と違いについて講義します。
<講師> 丸山 俊明(まるやま としあき)
<日時> 2025年 4月25日(金)19:00~20:30
<場所> 会場: Zoom配信
<参加費> 令和7年度(2025年度)伝統建築研究科受講生 無料
一般 2,000円
Peatix(『江戸の町家・京の町家』)でお申し込みください