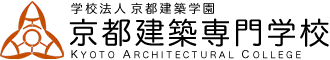| 第1回 昭和63年 「木造の魅力」 | |
| 文化財建造物の修理(10/22) | (財)建築研究協会建築部長 西田 義雄 |
| 文化財保護の見地から(10/22) | ㈱桝谷設計技術部長 宮内 幸一 |
| 日本建築の様式と技術の変遷(10/29) | 建築史家 前 久夫 |
| 茶室のきまり(10/29) | 裏千家今日庵営繕部長 根岸 照彦 |
| 京都の景観 ─歴史都市の再生(11/5) | 京都市住宅局 立入 慎三 |
| 私の住宅観(11/5) | STUDIO TOMITA 冨田喜一郎 |
| 木造住宅の設計を通じて(11/12) | ㈱建築環境研究所所長 吉村 篤一 |
| 京のまちやとその保存(11/12) | 京都大学建築学科助手 山崎 正史 |
| 壁から見た日本の建築(11/19) | 関西大学教授 山田 幸一 |
| 木造建築の構成(11/19) | 安井杢工務店副社長 安井 清 |
| 第2回 平成元年 「京の町家をささえる職人と技術」 | |
| 町家の庭(10/14) | 京都府造園協同組合顧問 豊田 英次 |
| 環境設計における庭(10/14) | 京都大学工学部助手 広川 美子 |
| 瓦と屋根構造(10/21) | 京の名工受賞者 梅垣 勘一 |
| ㈱大仏代表取締役 佐藤 滋朗 | |
| 京壁のあれこれ(10/28) | 京都府左官高等職業訓練校指導員 浅原 雄三 |
| 同 校長 佐藤嘉一郎 | |
| 第3回 平成2年 「今、和風建築を考える」 | |
| 木を知る(10/13) | 京都工芸繊維大学 中村 昌生 |
| 畳を知る(10/13) | 宮内庁 佐藤 理 |
| 壁を知る(10/20) | 関西大学 山田 幸一 |
| 日本住宅・来し方行く末(10/20) | 大阪工業大学 前 久夫 |
| 風土について(10/27) | 京都大学 加藤 邦男 |
| 棟梁の知恵(10/27) | 京都工芸繊維大学 日向 進 |
| 第4回 平成3年 「町家のうちそと」 | |
| 伝統民家に見る先人の英知(10/12) | 奈良女子大学名誉教授 花岡 利昌 |
| 京唐紙の歴史と技法(10/12) | 唐長11代当主 千田 竪吉 |
| 京都の近代建築(10/19) | 京都大学助手 石田潤一郎 |
| 京建具の伝統(10/19) | ㈱徳田代表取締役 徳田 敏昭 |
| 民家の再生(10/26) | アトリエRYO主宰 木下 龍一 |
| 京大工苦労話(10/26) | 京都府建築工業協同組合理事 米田 政司 |
| 第5回 平成4年 「伝統の技と心」 | |
| 大本長生殿造営苦労話(10/17) | 長生殿造営局設計部長 近江 清 |
| 桂離宮茶屋の修理(10/17) | 元桂離宮修理事務所員 建部 恭宣 |
| 京表具について(10/24) | 表具師・松村泰山堂社長 松村 好得 |
| 建築職人と道具の歴史(10/24) | 建築史家・樟蔭女子短期大学講師 前 久夫 |
| 木の魅力と人間(10/31) | 京都大学教授 田中 喬 |
| 京数寄屋の技(10/31) | 鈴木工務店社長 鈴木 義計 |
| 第6回 平成5年 「伝統の知恵から」 | |
| 現代の京数寄屋(10/23) | ㈱上野工務店会長 上野 富三 |
| 木造建築における竹の役割(10/23) | 京都竹材商業協同組合理事長 横山 伊助 |
| 銘木の話(10/30) | 京都銘木協同組合理事長 西村 友一 |
| 錺金具の伝統から(10/30) | ㈱森本錺金具製作所代表取締役 森本安之助 |
| 知恩院三門の修理(11/6) | 元京都府文化財保護課専門員 三上 皓造 |
| 地震と五垂の塔 ─心柱紀行(11/6) | 京都工芸繊維大学教授 石田 修三 |
| 第7回 平成6年 「100年後に向けて」 | |
| 木の心 ─数寄屋棟梁としての木の話(10/15) | 中村外二工務店棟梁 中村 外二 |
| 木造建築の可能性を探る(10/15) | 京都大学教授 内井 昭蔵 |
| 羅城門復元 ─「甦る平安京」出展に寄せて(10/22) (シンポジウム) |
京都府建築工業協同組合理事長 福井 晟 |
| 国際日本文化研究センター教授 村井 康彦 | |
| 京都大学名誉教授 金夛 潔 | |
| 建築史家 前 久夫 | |
| ㈱奥谷組工務課長 三井 敏弘 | |
| 司会 京都建築専門学校教員 佐野 春仁 | |
| ある明治期の大工の軌跡(10/29) | 関西大学教授 永井 規男 |
| 現代に生きる京指物の心(10/29) | ㈲江南・木工芸家 和田伊三郎 |
| 第8回 平成7年 「木と共に暮らす」─日常の暮らしと災害 | |
| 在来伝統木構造の強さ ─震災と人災─(10/14) | 匠頭─心傳庵数寄屋研究所 木下 孝一 |
| 伝統木構造の耐震性を考える ─阪神大震災が教えるもの─(10/14) |
京都大学講師 西澤 英和 |
| 町家の地方性(10/21) | 京都府立大学助教授 大場 修 |
| 塗壁の得失を見直す(10/21) | 佐藤左官工業所代表 佐藤嘉一郎 |
| 町家の暮らし(10/28) | 小島家当主 小島 正子 |
| 町家の生活と安全(10/28) | 町家再生研究会幹事 野間光輪子 |
| 第9回 平成8年 「次代へ伝える」 | |
| 文化財建造物の構法の歴史的変遷について(10/19) | 京都大学名誉教授 金夛 潔 |
| 集成材を使った大型木造構築物(建物・橋)のはなし(10/19) | 京都大学助教授 小松 幸平 |
| 文化財建造物の彩色復原について(10/26) | 川面美術研究所長・日本画家 川面 稜一 |
| 京都建築専門学校講師 三上 皓造 | |
| 庭と庭園の接点について(11/2) | 京都にわ耕主宰・造園作家 岡本 耕蔵 |
| 民家のいのち(11/2) | 建築家 瀧澤雄一郎 |
| 京の大工組について(11/9) | 京都大学名誉教授 川上 貢 |
| 茶室が出来るまで(11/9) | “京の現代の名工”府優秀技能者・会社社長 山本 隆章 |
| 第10回 平成9年 | |
| 1930年代からの和風 ─西川一草亭と堀口捨巳─(10/18) | 文化環境計画研究所・京都建築専門学校講師 中村 利則 |
| 和釘と手造り金物の製作について(10/18) | 横山金具製作所所長 横山 義雄 |
| 生命材料としての木材素材の機能を生かすには ─木材の燻煙熱処理について─(10/25) | 京都大学木質科学研究所物性制御研究室助手 野村 隆哉 |
| 茶室が出来るまで ─棟梁の仕事─(10/25) | “京の現代の名工”府優秀技能者・会社社長 山本 隆章 |
| 明治期の住宅建築について(11/1) | 滋賀県立大学助教授 石田潤一郎 |
| 寿山荘の普請について(11/1) | 安井杢工務店副社長 安井 清 |
| 第11回 平成10年 | |
| 瓦葺き建築の用と美(10/17) | 瓦葺き師・㈱磯崎瓦店代表取締役 磯崎 幸典 |
| 神戸の文化財建造物再生について(10/17) | 神戸市教育委員会教育部文化財課 佐藤 定義 |
| 居住空間における木材の「なごみ」効果について(10/24) | 京都大学大学院農学研究科教授 増田 稔 |
| 住宅と健康─ハウスドクターのすすめ(10/24) | 健康住宅推進協議会常務理事 工学博士 石本徳三郎 |
| 文化財建造物の塗装修理(10/31) | ㈲さわの道玄 代表取締役 澤野 道玄 |
| 伝統建築の鑑賞のしかた(10/31) | 全国国宝文化財所有者連盟事務局長 多福院住職 後藤佐雅夫 |
| 第12回 平成11年 | |
| 人にも地球にもやさしい塗料うるし(10/16) | ㈱加藤小兵衛商店代表取締役 加藤 二郎 |
| 本願寺西山別院本堂修理について(10/16) | 京都建築専門学校校長 三上 皓三 |
| 地震にも備えた伝統民家の若返り術(10/23) | 秋田県立大学木材硬度加工研究所教授・金沢工業大学名誉教授 鈴木 有 |
| 数寄屋の壁と対話する(素材と道具)(10/23) | 数寄屋左官 杉森 義信 |
| 西山別院修理工事現場見学と説明(10/30) | 京都建築専門学校校長 三上 皓三 |
| 第13回 平成12年 | |
| 葭屋町の町家改修─パネルディスカッションと見学(10/14) | 葭屋町大工棟梁 木村 忠紀 |
| 秋田県立大学木材硬度加工研究所教授・金沢工業大学名誉教授 鈴木 有 | |
| 田原建築設計事務所・木構造研究所 田原 賢 | |
| 佐藤左官工業所代表 佐藤嘉一郎 | |
| 文化環境計画研究所 中村 利則 | |
| 石との出合い(10/21) | 建築家・大阪市立大学生活科学部教授 竹原 義二 |
| 穴太衆の石積み(10/21) | 石匠 粟田 純司 |
| 対談 竹原義二 × 粟田純司(10/21) | |
| 伝統技能の実演(10/28) | 漆塗り・柿渋・ベンガラ 川崎 吉三 |
| 伝統土壁 京都左官組合 林 正信 | |
| 14回 平成13年 | |
| 数寄屋の中の寝殿(10/6) | 池坊短期大学助教授 岩崎 正弥 |
| より良い住まいと性能表示制度(10/6) | ㈲アトリエ803代表取締役・本校講師 田村 哲夫 |
| 建具の魅力(10/20) | 国の選定保存技術(建具制作)保持者 京都府教委文化財保護課嘱託員・建具工 鈴木 正 |
| 環境問題と建築の仕事(12/8特別公開講義) | 秋田県立大学木材硬度加工研究所教授・金沢工業大学名誉教授 鈴木 有 |
| 第15回 平成14年 | |
| 庭は生きている(10/12) | 京都造形芸術大学助教授・農学博士 仲 隆裕 |
| 星岡茶寮と近代数寄屋の拡がり(10/12) | 京都建築専門学校・工学博士 桐浴 邦夫 |
| 表具の技法─表具の仕事の面白さ(10/19) | 装潢師 松村 好得 |
| 四国の杉にこだわって─持続可能循環型の家づくり(11/16特別公開講義) | |
| 杉の話・林業家は家づくりの一番バッター | TSウッドハウス理事・親和木材㈱代表取締役 和田 義 |
| 杉の家づくり | ㈲六車工務店代表 六車 昭 |
| ディスカッション「川上と川下を結ぶもの」 | 和田義行 六車昭 六車俊介 他 |
| 司会:本校教務主任 佐野 春仁 | |
| 第16回 平成15年 | |
| 日本庭園の美 ─歴史と重森三玲・完途の作品(10/4) | ㈲重森庭園設計研究室 重森 千青 |
| 二条城の模写事業(10/18) | ㈲川面美術研究所所長 荒木かおり |
| 西本願寺の御影堂彩色補修(10/18) | 同 御影堂現場主任 仲 政明 |
| 大徳寺唐門彩色復原(10/18) | 同 唐門現場主任 出口 瑞 |
| 伝統土壁の力(12/6特別公開講義) | |
| 土壁の耐震メカニズム | 近畿大学助教授 村上 雅英 |
| 土壁の防火性能 | 早稲田大学教授 長谷見雄二 |
| シンポジウム「伝統土壁の力」 | 鈴木 有 長谷見雄二 村上雅英 木村忠紀 |
| 第17回 平成16年 | |
| 韓国の建築と空間─河回村集落の風景をめぐって(10/16) | 京都大学人間・環境学研究科助教授 西垣安比古 |
| 文人たちの数寄空間─田能村直入の動向を中心に(10/16) | 京都工芸繊維大学造形工学科助教授 矢ヶ崎善太郎 |
| 檜皮葺の技法 解説及び材料拵えと施工の実演(11/20) | 岸田工業株式会社代表取締役 岸田 重信 |
| 構造システムとして木造住宅を造る(12/4特別公開講義) | 丹呉明恭建築設計事務所代表 丹呉 明恭 |
| 山辺構造設計事務所代表 山辺 豊彦 | |
| 第18回 平成17年 | |
| 歴史都市比較で見る京都の町並み(10/15) | 立命館大学産業社会部教授 リム・ボン |
| 琉球の住まいと祭祀世界(10/15) | 京都大学大学院 人間・環境学研究科教授 伊従 勉 |
| こけら葺の技法 材料拵えと施工(11/19) | 岸田工業株式会社代表取締役 岸田 重信 |
| 京都迎賓館建設工事─平成の名建築をめざして(12/10特別公開講義) | 元迎賓館建設工事JV統括部長 水本 豊弘 |
| ㈱安井杢工務店工務部長 安田 邦雄 | |
| 第19回 平成18年 | |
| 茶室建築の見かた(10/14) | 京都建築専門学校伝統建築研究科教員 桐浴 邦夫 |
| 社寺建築の見かた(10/14) | 京都建築専門学校校長・伝統建築研究科主任 三上 皓造 |
| 瓦 講演と実演(11/18) | ㈱寺本甚兵衛製瓦 代表取締役代表 寺本 光男 |
| 新しい京町家をつくる(12/2特別公開講義) | |
| 基調講演 | 京都大学防災研究所教授 鈴木 祥之 |
| パネルディスカッション | 京町家震動台実験研究メンバー |
| 第20回 平成19年 | |
| F.L.ライトの遺言(7/7) | 福山大学工学部専任講師 水上 優 |
| モダニズムと数寄屋(9/29) | 京都建築専門学校伝統建築研究科教員 桐浴 邦夫 |
| 京町家の保存・再生(10/13) | 一級建築士事務所 アトリエRYO開設者 木下 龍一 |
| 京都の町家と町なみ(10/13) | 住環境文化研究所代表・京都建築専門学校伝統建築研究科講師・学術博士 丸山 俊明 |
| 本願寺御影堂の障壁画修理(11/17) | ㈱宇佐美松鶴堂代表取締役 宇佐美直秀 |
| 本来の木の家づくりを広げるために(12/15特別公開講義) | |
| 講演 | 木庸社(国産材プロデュース・建築設計)戸塚 元雄 |
| 自由討論 | コメント 木の住まい考房 鈴木 有 |
| 司会 | 本校教務主任 佐野 春仁 |
| 第21回 平成20年 | |
| ルイス・カーンとアルヴァ・アアルトの住宅の魅力(7/5) | 京都大学名誉教授、前田忠直建築研究所所長 前田 忠直 |
| 近代の建築にみる赤煉瓦(10/11) | 大阪歴史博物館学芸員 酒井 一光 |
| タイル考古学からみた近代建築(10/11) | 兵庫県教育委員会文化財室審査指導係長 深井明比古 |
| 討論「近代建築の保存活用と材料」 | |
| 石工事と文化財(11/15) | 石茂 ㈱芳村石材店代表取締役 芳村 誠二 |
| 町家と新たな街並み景観─現代を豊かにする歴史の力(12/13特別公開講義) | |
| 基礎講演「京都の新景政策と街並み景観主要構成要素としての伝統町家、和風意匠装置について」 | 建築家 武庫川女子大学教授 京町家再生研究会理事長 大谷 孝彦 |
| シンポジウム | |
| 現代を豊かにする歴史の力を | 大谷 孝彦 |
| 京都に相応しい潤いのある町並みを | 京都精華大学、武庫川女子大学等 非常勤講師 吉村 篤一 |
| 現代の京都に応える住居モデルを建築 | ㈱木村工務店社長 京都建築専門学校理事 木村 忠紀 |
| 庶民の町家を残して欲しい | フリーライター 内藤 恭子 |
| 司会 | よしやまち町家研究室 本校教務主任 佐野 春仁 |
| 第22回 平成21年 | |
| 建築から読み解く古都の近代 ~平安女学院 明治館と聖アグネス教会堂にて(7/4) | 京都工芸繊維大学教授 中川 理 |
| 左官技術の可能性 ~京都の技術から新しい空間を考える(10/10) | 左官職人 久住 鴻輔 |
| 建築家 森田一弥建築設計事務所代表 森田 一弥 | |
| 座談会 進行 | 本校教務主任 佐野 春仁 |
| 生きている本当の畳(11/14) | 国選定保存技術保持者(技術名称 畳製作)、畳三 中村三次郎商店 店主 中村 勇三 |
| 伝統構法の木造住宅はほんとうに大地震を凌げるか(12/12特別公開講義) | |
| 第一部 三者独談「伝統構法に関わる自分の立ち位置を語る」 | |
| この時代の大工の使命 | 宮内建築 代表、甲賀森と水の会 副代表 宮内 寿和 |
| 地震に対する安全性は法律や基準で担保できない | 三和総合設計株式会社、木造在来工法住宅を考える会(木考塾)代表 岩波 正 |
| 伝統構法に向き合って依頼の歩みを顧みる | 金沢工業大学・秋田県立大学名誉教授 鈴木 有 |
| 第二部 四者論談 最近の地震被害や震動台実験からどう読み解くか? “伝統構法の木造住宅はほんとうに大地震を凌げるか?” | |
| 第23回 平成22年 | |
| 「近代建築を学ぶ」シリーズ vol.4(7/3) 都市に住まう~歴史的視点から最近考えていること |
総合地球環境学研究所 東京大学生産技術研究所 教授 村松 伸 |
| 民藝について(10/16) | |
| 建築の民藝運動 | 京都市文化財保護課 石川 祐一 |
| 伝統を住みこなす─濱田庄司を中心に─ | 南山大学文学部准教授 濱田 琢司 |
| 座談会 進行 | 本校教員 桐浴 邦夫 |
| こけら葺きについて(11/13) | 有限会社屋根惣 代表取締役 杉本 惣一 |
| 京北合併記念の森に期待する(12/11特別公開講義) | |
| 基調講演“日本に健全な森をつくり直すために” | 京都大学名誉教授・「日本に健全な森を作り直す委員会」委員 竹内 典之 |
| パネルディスカッション | 京都大学名誉教授 竹内 典之 |
| 京都市林業振興課課長 三嶋 陽司 | |
| 京都市林業研究会会長 塔下 守 | |
| 京北森林組合参事 吹上 弘之 | |
| 京都大学准教授 神吉紀世子 | |
| いきもの多様性研究所 西本 雅則 | |
| 司会進行 | 本校よしやまち町家研究室室長 佐野 春仁 |
| 第24回 平成23年 | |
| 壁と窓─建築論的考察(5/28) | 京都建築専門学校 建築科二部講師 香西 克彦 |
| 法会の形式から見た寺院建築の平面と構造(5/28) | 環境事業計画研究所 北岡 慎也 |
| 和風建築について(6/18) | 京都工芸繊維大学 名誉教授 中村 昌生 |
| 木に生きる ~現代の銘木師を目指す(11/19) | 京都酢屋 ㈱千本銘木商会 常務取締役 中川 典子 |
| 環境時代の木造住宅 ~地域の山の木を活用した長寿命の家づくり(12/10) | MSD代表、京都造形芸術大学通信大学院教授 三澤 文子 |
| 第25回 平成24年 | |
| 創立記念講演「文化財修理工事の思い出」(6/30) ~慈照寺(銀閣寺)東求堂解体修理(昭和39・40年) ~清水寺釈迦堂<崖崩れ全壊>災害復旧(昭和48~50年) |
京都建築専門学校校長 三上 皓造 |
| 大工のつぶやき(11/17) | 京都建築専門学校 校長 福田 敏朗 |
| 大工道具の歴史 ~匠の技・ものづくりの心~(11/17) | 公益財団法人竹中大工道具館主任研究員 坂本 忠規 |
| 平成京町家の暮らし ~省エネ時代の生活文化(12/8) | 京都大学教授・平成の京町家コンソーシアム委員長 高田 光雄 |
| ㈱ゼロ・コーポレーション、㈱ステージホーム、㈱リヴ | |
| トヨダヤスシ建築設計事務所 所長 豊田 保之 | |
| 日暮れ手伝舎 吉田 玲奈 | |
| 同志社大学大学院 樋口 摩彌 | |
| 京都市住宅室技術担当部長 松田 彰 | |
| 第26回 平成25年 | |
| 「伝統建築の建築論」(6/15) | |
| 素材と制作 | 京都建築専門学校 建築科二部講師 香西 克彦 |
| 仏堂の展開とその背景─仏に人は如何に対峙してきたか─」 | 環境事業計画研究所 北岡 慎也 |
| 創立記念講演 「しる・すまう・なおす-京都の重要文化財民家-」(6/29) | |
| 京都の重要文化財民家の概要 | 京都建築専門学校 校長 福田敏朗 |
| 重要文化財民家に住まう-伊佐家住宅の保存と活用- | 伊佐家住宅 伊佐 錠治 |
| 重要文化財民家の保存修理について | 京都府教育庁指導部文化財保護課 森田 卓郎 |
| 千利休の茶室をめぐって(10/5) | |
| 千利休の茶室概要 | 京都建築専門学校教員 桐浴 邦夫 |
| 『山上宗二記』の利休像 | 帝塚山非常勤講師 神津 朝夫 |
| 対談『利休の茶室』 | 神津朝夫 × 桐浴邦夫 |
| 司会 | 京都建築専門学校校長 福田 敏朗 |
| これからの京都にふさわしい木造の家を考える ~伝統とどう向き合うか?~(12/14) | |
| 平成の京町家の試み | 京都大学院工学研究科教授・平成の京町家コンソーシアム委員長 高田 光雄 |
| 伝統の構法を残す意味 | 京都府建築工業協同組合理事長 木村 忠紀 |
| 温熱環境について─実測調査から報告とコメント | 京都大学大学院工学研究科助教 伊庭千恵美 |
| 自然と親しい長屋の住まい | 日暮手傳舎代表 吉田 玲奈 |
| 京都の都市構造と町家 | 魚谷繁礼建築研究所代表 魚谷 繁礼 |
| 第27回 平成26年 | |
| 創立記念講演 「きく・しる・まなぶ」(6/21) | |
| 平等院庭園について ─創建当時の浄土庭園─ | 宇治市歴史まちづくり推進課 杉本 宏 |
| 平等院鳳凰堂の建築 ─その変遷と平成修理─ | 京都府教育庁指導部 文化財保護課、平等院鳳凰堂保存修理事務所 島田 豊 |
| 伝統と現代─若手建築家のまなざし(10/4) | |
| これからの京都空間の可能性とその創生 | 建築家・一級建築士、㈱ローバー都市建築事務所 代表取締役 野村 正樹 |
| 伝統から発想する建築の可能性 | 建築家・左官職人、森田一弥建築設計事務所 代表 森田 一弥 |
| シンポジウム─ 京都にふさわしい住まいに望まれる快適さとは?(12/13) | |
| パネリスト | 京都大学教授 髙田 光雄 |
| 京都大学助教 伊庭千恵美 | |
| 国立技術政策総合研究所 三浦 尚志 | |
| 京都大学大学院 森重 幸子 | |
| 池田医院院長 池田 文一 | |
| ㈲古都デザイン代表取締役 山本 剛史 | |
| 京都市住宅室住宅政策課係長 青 木 厳 | |
| 司会 | 京都建築専門学校 佐野 春仁 |
| 第28回 平成27年 | |
| 創立記念講演会 「きく・しる・まなぶ」(6/27) | |
| 重要文化財 京都府庁旧本館における旧議場の復原と活用 | (一財)建築研究協会 主任研究員 野々部 万美恵 |
| 府県庁舎の価値と保存活用 | 京都工芸繊維大学教授 石田 潤一郎 |
| 武田五一と和風(11/3) | |
| 武田五一と伝統構法/武田グループの活躍 | 修復建築家、京都建築専門学校講師 円満字洋介 |
| 武田五一の茶室研究と和風/武田五一が千利休い見たものは・・・ | 都建築専門学校 伝統建築研究科主任 桐浴 邦夫 |
| 都市デザインにおける和風/武田五一が関わった街灯や橋梁デザインなどに見られる和の要素 | 京都工芸繊維大学教授 中川 理 |
| シンポジウム─京都に住まう(1/23) | |
| 平成の京町家 南禅寺の家 | 住まい手+設計者 |
| 平成の京町家 東山八坂通 | 住まい手+設計者 |
| 改修町家 N邸 | 住まい手+設計者+研究者 |
| コメント | 京都大学大学院工学研究科教授 高田 光雄 |
| 司会 | 京都建築専門学校 佐野 春仁 |
| 第29回 平成28年 | |
| 創立記念講演(7/9)桂離宮-その美しさの秘密を語る | 京都女子大学教授 斎藤 英俊 |
| 桂離宮昭和大修理 御殿整備工事の現場から(11/26) | 元㈱大林組桂離宮工事事務所所長・現㈱安井杢工務店顧問 水本 豊弘 |
| シンポジウム─京のまちに住む(12/10) | |
| 京の町衆の暮らしと文化 | 京都造形芸術大学教授 五島 邦治 |
| 町家を通してまちに住む(町家住まい手) | 浜谷冨美子・永井 美穂・柴田 晴美・井上 裕子 |
| まちの番人として | エステイト信 井上 信行 |
| 司会 | 京都建築専門学校校長 佐野 春仁 |
京都建築専門学校は、一部の教育プログラムを広く社会に開放し、多様化した時代にふさわしい生涯学習の実現を目指しています。
...
京都建築専門学校は、戦後間もなく、京都の大工職組合の子弟教育に始まりました。それから60余年、建築をとりまく状況が著しく変わりつつある中、本...
■2025年度二級建築士試験受験対策講座開講のお知らせ■
各学科の出題傾向を分析して出題される可能性のある重要事項について重点的にレク...
建築の設計作業は、3次元の建築空間をイメージし、いろいろな角度から検討を行い、それを2次元の図面にまとめていきます。
これはなかなか難しい...